-
診療科目
診療科目ガイド
お勧めコンテンツ
当院の診療科目
消化器内科
内科
禁煙
喫煙と禁煙
たばこを止めよう!
警告
禁煙指導・支援
禁煙の効果
たばこと健康
受動喫煙
たばこの有害物質
糖尿病
高血圧
脂質異常症
脂質異常症とは
高尿酸血症
高尿酸血症とは
肥満・メタボ
肥満とは
骨粗鬆症
睡眠障害
認知症
その他
その他の診療科目
サルコペニア
フレイル
-
診療案内
ご案内
検査・設備
健康管理
予防接種
-
当院について
クリニック紹介
基本理念・行動指針
院長挨拶
院内紹介
院内風景
-
通信
お知らせ
お問い合わせ
お問い合わせ
ひまわり通信
院長の独り言
目次
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
- リンク
- アクセス

スマホ用QRコード
肺炎球菌ワクチン
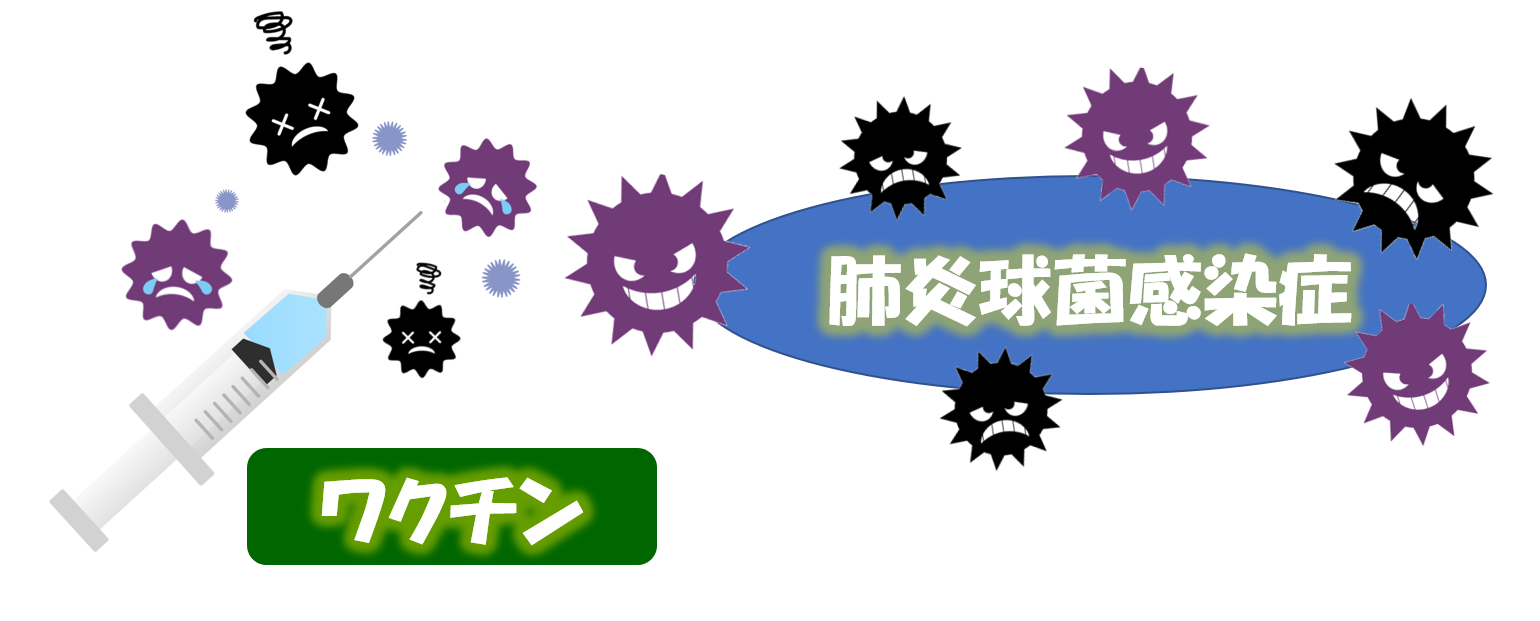 |
| 高齢者用肺炎球菌ワクチンが定期接種になりました |
平成26年10月1日より高齢者用肺炎球菌ワクチンが定期接種になりました
定期接種(公費助成)となるのは平成27年度から「該当する年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方」でしたが、令和6年度から「接種時点で満65歳の方」となりました。また、60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方はも従来通り定期接種の対象となります。ただし、すでに「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」を接種したことがある方は、対象とはなりません。
しかし、プレベナー(沈降13価肺炎球菌結合ワクチン)は定期接種として使用できません。任意接種(自費)となります。ただし、13価肺炎球菌ワクチンを接種したことがある場合でも「23価肺炎球菌ワクチン」を定期接種することはできます。
【リンク】
| 高齢者用肺炎球菌ワクチンについて |
■高齢者と肺炎
肺炎はわが国の死亡原因の第5位(7.5%)です。細菌によって生じる肺炎の原因の第1位が肺炎球菌によるもので約20%を占めています。また、肺炎で亡くなる方の97.8%が65歳以上の高齢者で年齢が上がるごとに死亡リスクが高くなります。80歳以上になる脳血管疾患と順位が入れ替わり第3位となっています。従って、65歳以上の方は肺炎球菌などによる肺炎を予防することが重要になります。
■高齢者用肺炎球菌ワクチン
①ニューモバックス:肺炎球菌には90種類以上の血清型があり、平成26年10月からの定期接種で使用される23価肺炎球菌ワクチン(一般名:23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン、商品名:ニューモバックス NP)は、そのうちの23種類の血清型を予防の対象としたワクチンです。この23種類の血清型は、平成25年には成人における侵襲性肺炎球菌感染症の原因の約6 割を占めるという研究結果があります。
②プレベナー13:ニューモバックスは23種類の血清型に対応したワクチンですがその免疫記録が持続しない(すなわち「効果が長続きしない」)とされています。そこで、ニューバックスとの併用接種で免疫記録が残る(効果が長続き)とされ両者の併用が勧められています。ただし、令和6年10月からプレベナー13に7種類の血清型が追加されたプレベナー20の使用が可能となり、以後はこちらのワクチンに切り替わっています。
③バクニュバンス:2024年4月からはじまったワクチン。プレベナー13よりも2つ多くの型をカバーしている。
④プレベナー20:プレバナー13の改良型ワクチンで20種類の血清型に対応したワクチンです。そのため、特にニューモバックスと併用しなくてもこのワクチン接種の1回接種することも可能です。過去にプレベナー13やニューモバックス23を受けた方でもプレベナー20の1回接種が受けることができます。現時点では最も推奨される高齢者用肺炎球菌用ワクチンです。
■副作用について
最近実施された臨床試験では75.4%に副反応が認められました。その主なものは注射部位の症状(痛み、発赤、腫れ)、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などがあります。
重篤な副反応としては、強いアレルギー反応(アナフィラキシー)、血小板減少性紫斑病、知覚異常・ギランバレー症候群等の急性神経根障害、蜂巣炎・蜂巣炎様反応(いずれも頻度不明)があげられています。 接種後に気になる症状や体調の変化があらわれたら、すぐ医師にご相談ください。

